 2026年
2026年 
| 紛争でしたら八田まで / ヘンリー・ジェイムズ短篇集 / カラマーゾフの兄弟 / 文章読本 / モンテ・クリスト伯 |
--- 紛争でしたら八田まで ---by 田 素弘 |


総選挙の最中、麻生太郎元総理のインタビューをユーチューブで見ていた。さまざまな質問のあい間に、最近読んだ漫画は?、と聞かれた。漫画オタクの麻生氏は、おめえらにはわかんねえだろうな、という表情で、本書の題名をあげた。すぐ次の質問へ移り、麻生氏の予想通り質問した記者はこの漫画を読んでいないようだった。 筆者も子供時代以外にはほとんど漫画には触れていない。漫画に関して何を言われても、へー、としか答えられない。 どんな質問にも皮肉を効かせてまともに答える麻生氏のような人が感心する漫画というのはどのようなものなんだろう。興味津々で購入してみた。 漫画とはいっても内容は硬派で、スラスラと読み進むことはできなかった。絵を見ながら、じっくり文章を読んでいくというやり方で、一冊読むのに結構時間がかかった。 第1巻は「ミャンマー企業紛争編」「タンザニア魔女狩り騒乱編」、第2巻は「イギリス酒場で酔狂乱闘編」「ウクライナ愛と暴力と資金提供編」となっている。それぞれの紛争地帯で地政学リスクコンサルタントの八田百合が大活躍する。彼女の武器はプロレス技。1、2巻で繰り出した技は「シャイニング・トライアングル」「チキンウィング・スープレックス」「アナコンダバイス」「スリーパーホールド」「後ろ回し蹴り」など。銃器は苦手である。 日本は現在紛争地帯とはいえないが、尖閣列島や北方領土がいつ紛争地帯になるかわからない状況である。台湾海峡が紛争地帯になっただけでも、石油タンカーの航路が阻害され、日本経済に大きいダメージを与える。地雷が埋まっている地域を無防備で歩いているような状況ともいえる。世界で起きていることはいずれ日本でも起きる。すべての日本人はその意識を目覚めさせておく必要がある。 (2026.2.3) |

--- ヘンリー・ジェイムズ短篇集 ---by ヘンリー・ジェイムズ |
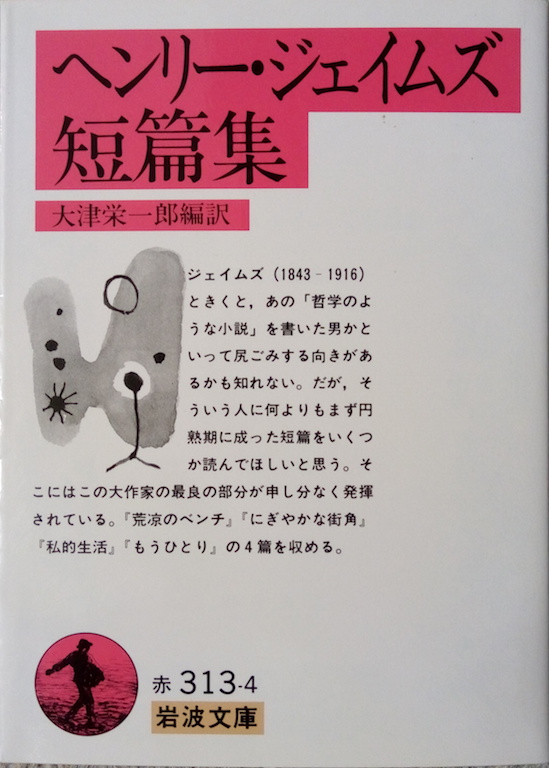
【私的生活】(The Private Life) スイスの景色の良いリゾートホテルに滞在中の男女。知り合い同士の何組かの男女が旅先での交際を楽しんでいる。語り手は作家。彼以外はカップルで滞在している。メリフォント卿は画家、クレア・ヴォードレーは作家、ブランチ・アドニーは女優、その夫はヴァイオリン奏者である。 ある時、ブランチ・アドニーは「クレア・ヴォードレーがふたりいるとすれば、メリフォント卿は結局ひとりもいないのではないかしらと思うのよ」と言い、それがこの小説のテーマになっている。公的生活と私的生活をはっきり区別する英国人の生活様式は、アメリカ人である著者には興味深いものがあるものと思われる。 著者はアメリカ人だが、最終的に英国のロンドンに永住した。作品のほとんどが英国を舞台にしている。 【もうひとり】(The Third Person) 2人のオールド・ミスが英国の古い屋敷を相続する。2人はいとこ同士だがそれまで面識はなかった。2人は屋敷を金に変えて分配するのではなく、そこに一緒に住むことにした。 小説は孤独な女性2人の共同生活を描いて、心の交流とすれ違いを書いている。原題「The Third Person」というのは、どちらかの部屋に現れる先祖の幽霊のことである。幽霊が若い男性であるので、2人の老嬢は大きな影響を受ける。幽霊が実在するものであったのか、老嬢たちの心に浮かんだ幻影であったのかはわからない。その辺の描写は「ねじの回転」の著者が得意とするところである。 【にぎやかな街角】(The Jolly Corner) ブライドンは33年ぶりにアメリカのブロードウェイにある古い屋敷に戻ってくる。そこは彼が子供時代に過ごした家だった。屋敷を相続した兄弟たちが亡くなり、彼が相続することになったからだ。彼はそこを売らずに、住むつもりでいる。その屋敷には何者かがいる気配がした。真夜中に彼がそこを訪れると、気配は実態となって姿を現した。指が2本かけていて怖い顔をした男だった。 アメリカに生まれ、33才でロンドンに移住した著者は、亡くなるまで英国で生活した。この小説はそうした彼の体験を小説化したものだろう。 【荒涼のベンチ】(The Bench of Desolation) 婚約不履行で訴えたケイトはハーバートから多額の賠償金を獲得した。ハーバートは長年の間少しずつ賠償金を支払った。結婚して子供も生まれたが、生活は貧乏だった。10年の間に子供は死に、妻も亡くなった。孤独になったハーバートのもとにケイトが現れた。「なぜ?」。いぶかる彼にケイトは、あなたの世話をしたい、という。 ー ー ー ー ー 解説者はヘンリー・ジェイムズの文学の特徴に、
の三つの要素をあげている。彼をジェイムズ・ジョイス、ヴァージニア・ウルフ、ウィリアム・フォークナーの先駆者として、二十世紀文学の創始者である、としている。 プロットが明確でロマンス性があり、登場人物たちは明確な意識を持ち、思い通りに行動する。19世紀の小説はわかりやすく、とらえやすかった。そういう小説を読みつけると、プロットがはっきりせず、登場人物たちはあっちへ行ったりこっちに来たり優柔不断で、フラフラしている思考をそのまま表現する20世紀小説は読みづらくもあり、新鮮でもある。数年ぶりにヘンリー・ジェイムズを読んで、以前読んだ時より主人公たちのことが理解できたかな、と思った。「ねじの回転」ももう一度読み返す必要があるだろう。 (2026.2.2) |

--- カラマーゾフの兄弟 ---by F.ドストエフスキー |


本書は第一部から第四部とエピローグという構成をとっている。第一部から第三部までは一日一部で、第一部から第三部までは三日間の出来事である。いろいろなことが起こるので、とても三日間の出来事とは思えないのだが。 主人公はドミートリイ・カラマーゾフという28才の退役軍人である。ドストエフスキーは前書きで、本書は主人公アレクセイ・カラマーゾフの青年時代の話である、とことわっている。

だが、本書の構成を考えると、第一部ではドミートリイと父親フョードルの財産争いが描かれ、第二部ではゾシマ長老の青年時代の話、第三部では3,000ルーブルを求めるドミートリイの奮闘とフョードルの死、ドミートリイの逮捕に至るまでのできごとが描かれる。第四部では殺人犯として起訴されたドミートリイの裁判の様子が描かれている。 かいつまんでいうと、本書はカラマーゾフ家の長男ドミートリイの災難と奮闘の物語である。 それだけでは世界文学の最高の作品といわれることはないだろう。太い幹にはさまざまな枝葉が生い茂って大樹となっている。物語はドミートリイの家族やその知り合いの関係がからみ合い、複層的に進んでゆく。 あまりにさまざまな話が出てくるので、時にはこの物語がドミートリイの冤罪事件であることを忘れてしまう。次兄イワンが「大審問官」の話を語りだすと、読者は思わず引き込まれてしまうだろう。筆者は、ゾシマ長老が若い時に出会った「神秘的な客」の話を読むたびに強烈な印象を受ける。また、三男アリョーシャが体験した「小悪魔」の章を読むとドキドキしてしまう。グルーシェニカが語る「一本の葱の話」に触発された芥川龍之介は「蜘蛛の糸」を書いた。 第四部の裁判の場面の長い論告シーンは退屈である。だがイワンが法廷で陳述しながら徐々に狂っていく場面と、それに呼応して冷静だったカテリーナが狂乱状態に変化する場面は迫力満点である。この部分を読むと、ビリー・ワイルダー監督の映画「情婦」の法廷の場面を思い出す。 イワンは「神がなければすべてが許される」といい、ドミートリイは「神がいなければ人間はどうやって善人になれるんだ」という。これは殺人の思想的な背景となっている。無神論者の筆者には理解できない考え方である。フョードルは「俺の考えでは寝入ったきり、もう二度と目をさまさない、それで何もかもがパアさ。供養したけれゃするがいいし、したくなけりゃ勝手にしろだ」という。登場人物の中で唯一無神論者なのが、殺されたフョードルなのは皮肉な話である。 もう1人無神論者がいる。アリョーシャの友人、グルーシェニカの従兄弟でもあるラキーチンだ。彼は「神がいなくたって人類を愛することはできる」という。彼はどこへでも出入りし、探り出したニュースを面白おかしく脚色して、雑誌に売り込む。まるで現代日本の新聞記者のような人物である。150年前に書かれたものであっても、作品が古びることがないのは、そこに生きている人間の本質は変わらないからであろう。 エピローグは、アリョーシャが12,3人の中学生とイリューシャの墓の前で将来の再会を誓う場面で終わる。いよいよ次の作品ではアリョーシャが主人公となり、別の物語が始まるのだ、という予告みたいな場面である。ドストエフスキーは本書を書いてから1年後の1881年、次の作品のノートを残して、59才で永眠してしまう。 (2026.1.26) |

--- 文章読本 ---by 向井 敏 |
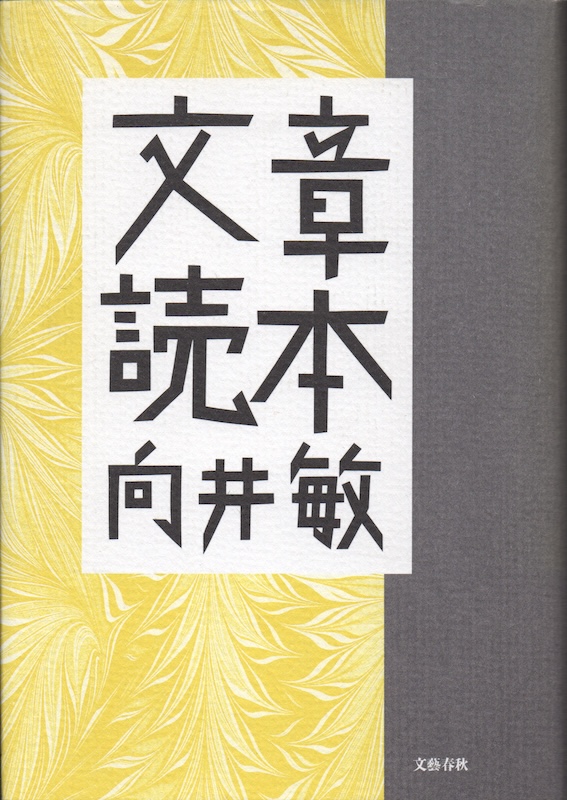
このHPで良い文章を書きたいのだが、どうとたら良いのかわからないでいる。何度か読み返してみて、不自然と感じないところでアップロードするようにしている。その文章も何時間か、あるいは何日か経つとなんとなく変に思えてくるので困っている。 著者は「文章のもつ快さ、あるいは不快さは作者の精神のあり方の如何にかかわるものであって、扱われている題材やテーマの暗さ明るさとは本来関係がない」と述べている。「精神のあり方」が重要とのことである。 著者は悪文の代表として野間宏と大江健三郎の文章を、明晰な文章の代表として倉橋由美子の文章を取り上げている。 それらの例文を読んでみると、前者は何を言いたいのかよくわからないのに対して、後者は言いたいことがはっきりわかる。前者は文章がくねくねとあっちへ行ったりこっちに来たりしてつかみどころがない。これは著者が自分の言いたいことがはっきりしていないためか、あるいは読者を混乱させることで、自分を高く見せようとしているのか。いずれにしても健全な精神でないことが推測される。 著者は「文体」について、「文章の気品」について、「文章のおしゃれ」について、「文章の効率」について述べ、最後に「起承転結の重要性」について述べて本書を締めくくっている。 著者の言葉に忠実に従えば、自分にも良い文章が書けそうな気がしてきた。 (2026.1.6) |

--- モンテ・クリスト伯 ---by アレクサンドル・デュマ |

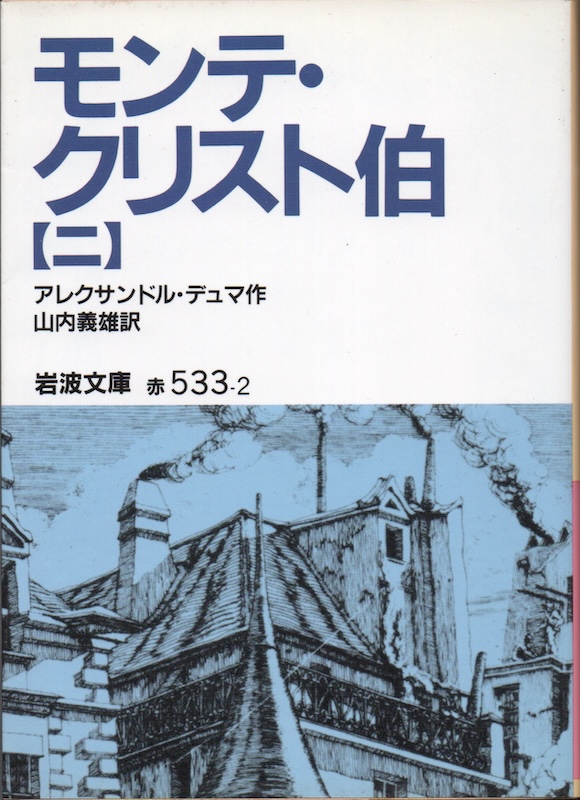
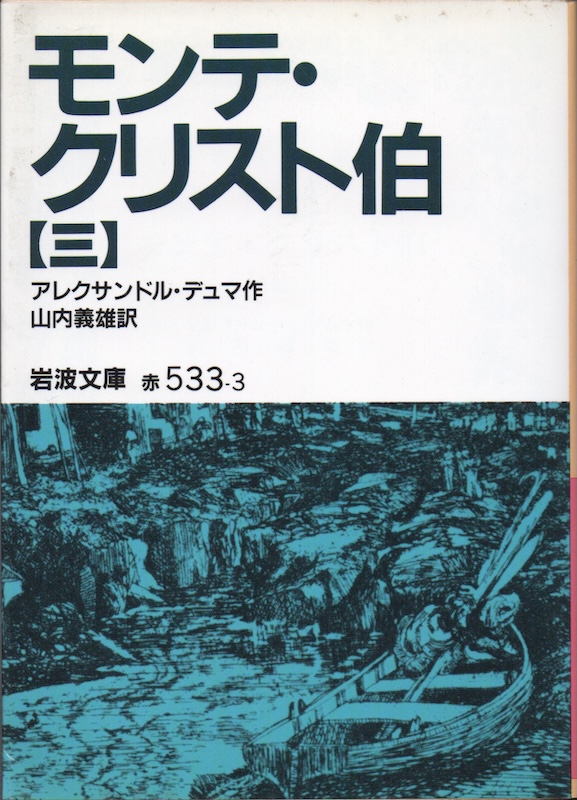

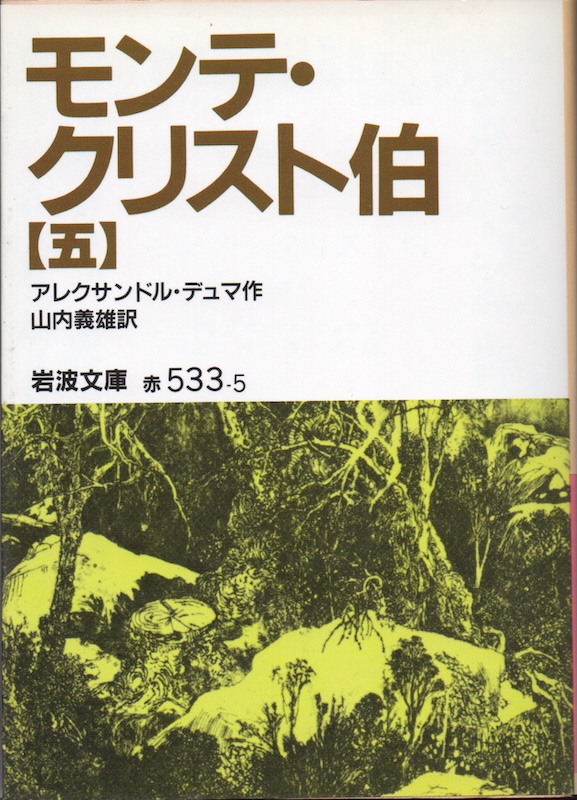

本作はアレクサンドル・デュマが39才から43才までに書いたものである。トルストイが「戦争と平和」を書いたのは36才から41才にかけて、ドストエフスキーが「罪と罰」を書いたのは45才の時という具合に、作家が彼の代表作を書く年齢は30代後半から40代までであろうと考えられる。 ダングラール、カドルッス、フェルナンという三人の若者が旅館「ラ・レゼルヴ亭」の脇の葡萄棚の下でワインを飲んでいる。「ラ・レゼルヴ亭」ではエドモン・ダンテスとメルセデスの婚約パーティが行われている。ダングラールはエドモンをおとしめるための密告状を書いている。 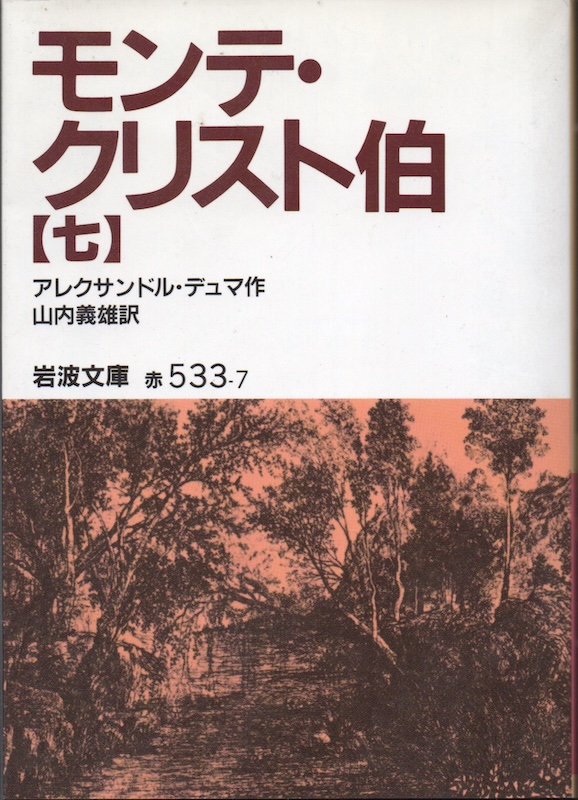
ダングラールが丸めて捨てた密告状をフェルナンが拾う。カドルッスはそれを見て見ぬふりをする。こうしてこの裏切りと復讐の物語は始まる。 この場面はまるで舞台劇のようで、シェイクスピアの悲劇のはじまりを彷彿させる。 ダングラールは年下のエドモンが自分を抜いて船長に抜擢されることに嫉妬し、フェルナンはプロポーズしたメルセデスがエドモンと婚約したことに嫉妬している。カドルッスはエドモンに悪意を持っていないが、心の弱い事なかれ主義の男であった。 世の中の悪は嫉妬心から始まる。傍観者はたいていの場合、悪い方に味方する。というテーマでこの長大な小説は始まる。 
ダンテスは14年間の牢獄生活を脱出し、10年かけて自分を落とし入れた4人に復讐する。復讐の方法はモンテ・クリスト伯爵として彼らに近づき、人為的とは思えないやり方で、彼らの運命の方向を少しだけ変えてやる。今ではそれぞれ社会の上層階級にいる裏切り者たちは少しずつ不幸になってゆく。 結果2人が亡くなり、1人は気が狂い、1人は社会的に破滅する。 本書は「巌窟王」として年少者向けに抄訳された、単純な復讐物語とは本質的に違う。デュマはモンテ・クリスト伯爵という超人を核にして、19世紀のフランスの風俗を描いたのだと思う。本書には風俗ばかりではなく、ミステリーや冒険や恋愛が含まれている。 モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンもの「奇岩城」、ジュール・ヴェルヌの「海底2万里」や「80日間世界一周」、エラリー・クィーンの「Yの悲劇」は本書に影響されて書かれたものと推測されるし、「海底2万里」のネモ船長や「80日間世界一周」のフィリアス・フォッグ氏にはモンテ・クリスト伯爵のイメージがある。さらに「Yの悲劇」の真犯人は本書の登場人物〇〇のイメージそっくりではないか。 三遊亭円朝が1859年に作った落語「真景累ヶ淵」の構造が本書に似ているというのはどうだろうか。グリム童話から「死神」を、モーパッサンの「親殺し」から「名人長二」を、サルドゥの「トスカ」から「錦の舞衣」を翻案した円朝である。本書にたびたび出てくる因縁奇縁の挿話を参考にして、あの壮大な因縁噺を作ったと考えるのもありではないだろうか。本書が出版されてから14年後に作られているので、可能性としてはあると思う。 本書に登場する山賊の首領ルイジ・ヴァンパは読書家で、あるときはシーザーの「ガリア戦記」、あるときはプルタルコスの「英雄伝」という具合に、登場するときはたいてい本を読んでいる。しかも通俗本ではなく、古典である。いずれも岩波文庫で出ているので、そのうちに読んでみようかと思う。 シャトー・ディフの牢屋でダンテスに学問を教えるファリア司祭はこういう。「世の中には物識りと学者のふた色があってな。物識りをつくるものは記憶であり、学者をつくるものは哲学なのだ」。180年前からすでに物識りが学者より巾をきかしていたのかもしれない。 アンドレアとの結婚を結婚式直前でキャンセルしたダングラールの娘ユージェニーは、女友達のルイーズ・ダルミイー嬢と一緒に逃げる。書かれたのが1945年だから直接的には書いていないが、この2人はレズである。180年前からそういう関係は存在し、それを小説に書いたデュマはジャーナリステックな小説家であったといえる。 この長大な物語の最後は「待て、しかして希望せよ!」という言葉で終わっている。これはエドモン・ダンテスの生涯を支えた言葉であり、180年後の読者に向けたデュマからのメッセージでもある。 (2026.1.3) |

Copyright(C) 2012 Umayakaji.com ALL rights reserved.